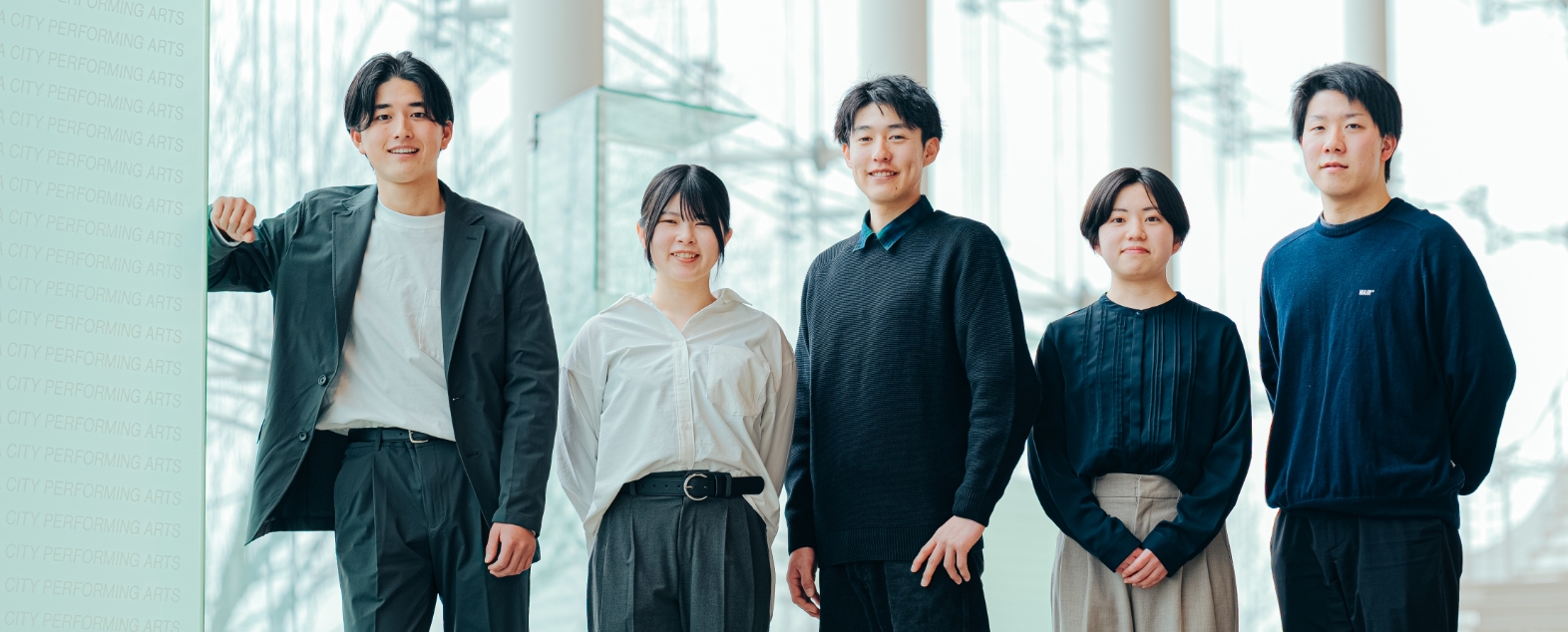ベテランと若手が語る、
「解体」という仕事の奥深さとは?

1960~1970年代、高度経済成長期に日本各地で建設が進められた巨大団地。近年老朽化が進み、順次、解体・建て替え工事が進められています。福田組が一部の棟(4号棟)の解体工事を行う、名古屋市「堀田団地」もその1つ。今回はこの現場の所長と所員3名で、「解体という仕事の奥深さ」をテーマにクロストークを開催しました。ただ壊すだけではない、奥の深い解体工事。その一端を垣間見ていただけるかと思います。
MEMBER
-

下澤 大輔
名古屋支店 土木部 工事担当
工事所長
1997年 新卒入社 -

赤塚 吉孝
名古屋支店 土木部 工事担当
工事副所長
1992年 新卒入社 -

飯塚 爽介
名古屋支店 土木部 工事担当
2023年 新卒入社 -

内藤 伶太
名古屋支店 土木部 工事担当
2025年 新卒入社
※所属および掲載内容は取材当時のものです。
実は着工前が一番大変!?知られざる解体工事のあれこれ

 下澤所長
下澤所長改めて解体工事について語り合うという貴重な時間をもらいましたので、進めてみたいと思います。まず、解体工事は初めての飯塚くん、携わってみて、どうかな?
 飯塚
飯塚そうですね。今は地上解体が始まって、階上解体時に使っていたものとは比べ物にならないくらいの大きな重機が配備されて、圧倒されています。安全管理もさらに気を付けなければ、と思っています。
 下澤所長
下澤所長今までの土木の現場との違いを感じたり、学びにつながったりしているところはある?
 飯塚
飯塚これまでは福島県でトンネルや車道の工事に携わっていて、周囲に人がいなかったんです。でもここは街なかで、すぐ隣の3号棟には住民の方がいらっしゃって…という状況なので、「常に人に見られている」という良い意味での緊張感があり、勉強になっています。所長の教え通り、住民の皆様には愛想よく!挨拶は元気よく!エレベーターの開くボタンもしっかり押しています!
 下澤所長
下澤所長いいね(笑)。飛散物や粉じんなど、周辺地域へも気を遣うからね。第三者への配慮に関しては、解体現場はすごく勉強になると思う。内藤くんはどう?入社して初の配属がここだけど。
 内藤
内藤まだ配属されて2カ月くらいなので、分からないことの方が多いのですが、早く「課題に気付けるようになりたい」と、皆さんの姿を見て思っています。
 下澤所長
下澤所長…と言うと?
 内藤
内藤皆さん、刻一刻と変わる状況に対して課題を認識し、協力会社さんと話し合い、1つひとつ解決して進められているじゃないですか。その姿がかっこいいな…と思って見ています。
(なんて素直な新入社員…!)
 下澤所長
下澤所長なるほどね。そんな風に見てくれていて、うれしいよ。赤塚さんはどうですか?本格的な解体現場はここが初めてですか?
 赤塚
赤塚そうですね、本格的なものはここが初めてです。特にここは都市部なので、近隣住民の皆さんへの配慮が大切だと身に染みて感じています。今まで経験してきた、地下トンネルや高速道路の工事では、そこまで強くは感じてこなかった部分かもしれません。あと、高所作業が伴う現場であることも、私にとっては緊張しました。土木って、普段そんなに高いところに上らないので…。
 下澤所長
下澤所長確かに!土木で高所作業ってあまりないですね(笑)。あと、みんな知ってる?解体工事は、実は着工前が1番大変なんだよ。
 赤塚
赤塚下澤所長以外の全員が、着工後に着任しているから、着工前の手続き・届け出は、ほぼ全部所長がやってくださったんですよね…(笑)。
 飯塚
飯塚そうなんですよね!いつも所長から「次は自分がやると思って見ておけよ!」って言われていますから。着工前のすごい量の書類にも目を通して、理解するようにします!今私が担当している産業廃棄物の処理に関する書類だけでも大変なので、着工前の届け出はもっと大変だっただろうな…と。
 下澤所長
下澤所長そうそう、届け出が複雑で膨大なんだよね。事前調査で現状を正しく把握して、1つひとつの届け出に必要な情報を集めて書類を作って許可を得て…という流れ。でもこれも、私たちのような工事関係者だけでなく、周辺住民の安全を守るための重要な仕事。きちんと届け出を行うことは、安全な工事が進められる状況を整えるってことだからね。

解体工事の現場は、状況と周囲の声に応じて変化する現場

 赤塚
赤塚計画通りにいかないことが前提…というか、考えていたことができない状況が起こるのが当たり前なのも、解体工事ならではだな、と感じています。
 下澤所長
下澤所長そうですね。他の工事では、こんなに計画変わらないですもんね…。
 赤塚
赤塚施工方法も、常に現場の状況に合わせて変えていきますからね。想定していたよりも固くて壊せないとか、周囲からの騒音の苦情とか、現場内外の状況の変化に合わせて変えていく必要があるんですよね。
 下澤所長
下澤所長現場に乗り込んでからでないと分からないことも多いですしね。図面を見ただけじゃ分からない。今回は1970年代前半に建てられた建物だから、図面も手描きでよく見えないんだよね(苦笑)。解体する建物はだいたい古い建物だから、これもあるあるだね。解体工事の現場はどこでも、状況と周囲の声に応じて柔軟な変更が必要とされるんだ。
 内藤
内藤皆さんが協力会社さんとよく話し合っているのも、都度、対応を検討して対処するために必要なんですよね。
 下澤所長
下澤所長そうそう。協力会社さんに「どうしたらいいと思う?」って相談しながら、常に模索しながらだね。やってみてダメだった…ってことも日常茶飯事。
 飯塚
飯塚今回の現場だと、やっぱり「線路に沿って建っている北側の壁」が1番の課題でしたか?
 下澤所長
下澤所長そうだね。電車が止まっている間、夜中の1~4時の3時間だけで、北側の壁の解体と足場の撤去をしなきゃいけなかったからね。最初はどうしようかと思ったけど、うまくいって良かった。
 飯塚
飯塚ケージシステム※を採用したことが大きかったですよね。私も初めて見ました。くるくるとハンドルを回すだけで、飛散防止ネットの高さが変えられる、盛り替えができるなんて画期的です。
 下澤所長
下澤所長ほんと、状況に合わせていろいろな人が知恵を出し合う、アイデアの結晶だよね、解体工事は。ケージシステムも発注者様の他現場での採用例があって、紹介してもらえて助かりました。
※通常の飛散防止ネットよりも、移動・盛り替えが簡単にできるシステム。これを採用することにより、夜間2時間の作業でも、朝から始まる工事への準備をスムーズに進めることができました。

状況に合わせた柔軟な発想と対応力を糧に

 下澤所長
下澤所長じゃあ最後に、少し目線を未来に向けてみましょうか。ここでの仕事を通して学んでいること、それをどう今後に活かすか、若手の2人から聞いてもいいかな?
 内藤
内藤私はこの現場が初めてなので、人とすごく近い場所に大きな重機があることに驚いていて、これは「気を抜いたら事故が起きるぞ」という危機感を持って現場に立っています。この危機感を忘れないようにしたいのと、あとはここで知った現場の知識や段取りなどは全て自分のものにして、次の現場でも活かしたいです。
 飯塚
飯塚私は先ほど所長が仰っていた着工前の手続き・届け出の書類も、「次はこれを自分でやるんだ」という気持ちで目を通し、知識を貯めていこうと思います。…ちょっと、膨大すぎて、ビビっていますが(苦笑)。
 赤塚
赤塚結局、このすごい量の書類を作るだけの知識が必要ってことだもんね。どうやったらここまで作れるんだろうって、私も所長が作った書類のファイルを見て思っています(笑)。あと、個人的にこの現場で鍛えられているのは、「その場で判断する力」と「周囲への配慮」。適切な判断で、現場を止めずに、かつ周囲の方への配慮も行き届いた対応ができた時はホッとします。
 下澤所長
下澤所長そうですね。社歴を重ねても、経験できる解体工事の現場は限られていますね。解体工事は、状況に合わせた柔軟な発想と対応力が鍛えられる、数少ない現場だと思う。飯塚くんや内藤くんは、若いうちにこの経験ができて良かったと思うよ。イチ工種として学べばいい。ぜひ今後の仕事に活かしてください。
 飯塚・内藤
飯塚・内藤はい!頑張ります!

仮配属に関するレポートについては、コーポレートサイトの FUKUDA JOURNAL もぜひご覧ください。
コーポレートサイト FUKUDA JOURNAL